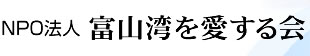2024年度 セミナー
テーマ 「日本海は地中海」
日 時 令和6年12月14日(土)午後2時~4時
場 所 川の駅新湊
講 師 金川欣二氏(富山高等専門学校名誉教授)
内 容 言語学が専門の先生は該博な知識をもとに地理,歴史,伝統,風俗などに見られる 類似性や共通点を指摘して北陸の諸都市をイタリアの有名都市に見立ててみせました。 例えばミラノと金沢には流行,伝統舞踊,民工芸品,建築に似た雰囲気があり,ナポリと 氷見には海の美景があり,ベニスと新湊には先述した多くの類似性があるといったお話しでした。 講演に先立ち,奥様の金川睦美氏がオペラ「ジャンニ・スキッニ」"お父さまにお願い"を歌唱され、 聴衆一同その本格的な美声に魅了されました。ジャンニ・スキッニ(父)にむかって娘が 「結婚を許してくれなかったらフィレンツェの中心ベッキオ橋からアルノ川に身を投げてしまうわ, と歌う場面とのことでした。
2024度 海藻おしば教室
日 時 令和6年12月5日(木
場 所 射水市立金山小学校
講 師 高山優美氏(海藻おしば協会)
参加者 5年生13名、教員・市役所職員・本会会員など15名
内 容 海藻おしば協会の高山優美先生ご指導のもとクイズやDVD鑑賞も交えて海藻の役割と 海の環境を学習しました。つづい,アオサ(緑藻),アカモク(褐藻),トサカノリ(紅藻)などを 材料に海藻おしばを製作しました。海藻の美しさや形の面白さとともに環境を良くする海藻の役割が 永く子供の記憶に残れば幸いです。
2024年度 歴史探訪街歩き
日 時 令和6年10月27日(日)
場 所 川の駅新湊~竹内源造記念館~庄川大仏~川の駅新湊
案 内
内 容 小雨降るなか小杉町の竹内源造記念館と砺波市の庄川大仏を訪れました。 竹内源造は小杉町出身の優れた腕利き左官職人で数々の芸術的な鏝絵(こてえ)を製作しました。 記念館では,龍,鳳,鶴,亀,アカンサス(草葉の装飾文様)など優美で格調高い作品を鑑賞し, 郷土の豊かな芸術風土にふれました。つづいて,砺波にある庄川大仏を見学しました。 この阿弥陀如来像も竹内源造の遺作で,光照寺の閑静な境内に堂々とおわしました。 知られざる文化遺産に出会うありがたい歴史探訪でした。